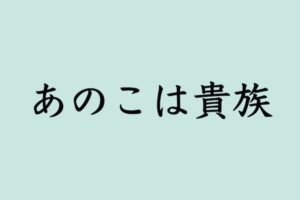こんにちは。織田です。
今回は2022年公開の『母性』をご紹介します。
廣木隆一監督。戸田恵梨香さん、永野芽郁さんが母娘を演じています。原作は湊かなえさん。
本記事では原作小説を読んだ上で映画を鑑賞した感想を書いていきます。
感想部分で作品のネタバレを含むため、未鑑賞の方はご注意ください。
あらすじ紹介
ある日、女子高生の遺体が発見される。事故や自殺か、あるいは他殺なのか、その真相は不明だった。悲劇に至るまでの過程が母・ルミ子(戸田恵梨香)と娘・清佳(永野芽郁)それぞれの視点で明らかになっていくものの、双方の証言は同じ出来事を回想しているにもかかわらず食い違い、母と娘の複雑な関係が浮き彫りになる。
スタッフ、キャスト
| 監督 | 廣木隆一 |
| 原作 | 湊かなえ |
| 脚本 | 堀泉杏 |
| 母 | 戸田恵梨香 |
| 娘 | 永野芽郁 |
| 娘(幼少期) | 落井実結子 |
| 母の実母 | 大地真央 |
| 母の夫・田所哲史 | 三浦誠己 |
| 母の義母 | 高畑淳子 |
| 母の義妹・律子 | 山下リオ |
| 母の友人・仁美 | 中村ゆり |
| 娘の友人・亨 | 高橋侃 |
| 同僚教師 | 淵上泰史 |
この映画では終盤までとにかく人物の名前が出てきません。
母(戸田恵梨香)にとっての義妹(永野芽郁にとっての叔母)である律子(山下リオ)、また母(戸田恵梨香)の絵画教室時代からの友人であり、夫の田所と幼い頃からの知人であもある仁美(中村ゆり)くらいです。
ほとんど全ての会話が「お母さん」「ママ」「おばあちゃん」「おばあちゃま」「あんた」「お前」で構成され、父親・田所(三浦誠己)の所在なさもあって「母」と「娘」の割合が特に多い形となっていました。
原作と映画
以下、感想部分で作品のネタバレや展開に触れていきます。未見の方はご注意ください。
映画『母性』の原作は湊かなえさんの小説です。
小説を既読していた立場からいうと、映画では原作のエピソードを一部省略したものになっていました。
小説では後半部分に母(映画版の戸田恵梨香)にある変化が訪れます。タイトルの『母性』にも大きく関わっていく出来事でしたが、映画版ではバッサリと省かれていました。
湊かなえ作品によく見られる衝撃的な展開や、イヤミスのドロドロした部分が映画『母性』ではそれほどまでに感じられなかった、という感想をいくつか拝見して私も同意なんですが、上記のエピソードが映画版にも盛り込まれていたら受ける印象も変わっていたのではないかと思われます。
一方でその小説のエピソードにはかなり精神的なダメージを受けたので、個人的に映画版の省略には納得でした。





加えて母と娘の前に起こった台風の夜の“事件”においても、原作から改変が見られました。これは視覚的にわかりやすくした形だと思います。
「驚き」の部分の担保
『母性』は3人の語り手によって物語が展開します。
母、娘、そして女子高生の遺体が発見されたニュースに関心を持つ教師の3人です。
小説を初めて読んだ時は「娘」と「教師」が同一人物であることに少なからず衝撃を受けました。しかし映画ではこの両者ともに永野芽郁さんを起用していることで、そのインパクトは薄まりました。
映画版で驚きを与えたのは戸田恵梨香の義妹にあたる田所律子(山下リオ)の存在です。
虚飾だらけのような男と駆け落ちの形で田所家を出ていった律子との再会は、永野芽郁が淵上泰史と飲んでいた居酒屋でした。怪しさ満点だった男も優しそうな笑顔を携えて働いていました。疑ってすみませんでした。
原作だと店員の「りっちゃん」はもっと前面に出てきてイコール田所律子と早々に繋がるんですが、映画の落としどころ、また見せ方は原作とは違う驚きを与えてくれていたと思います。
付け加えると、「律子ォ…」と泣き咽ぶ高畑淳子が抱きしめていた赤いクッションの背景については原作で言及されているので、未読の方は小説を読むとなるほど、となるかもしれません。
▘▛▝ ▘
母性が日本を惑わせるまで
🥀 あ と 1 週 間 🌹
▖▖▝▟⚠️クセ強キャラ大集合❗
⚠️すれ違う母娘の“母性”が暴走❗
⚠️誰も観たことがない母娘の物語❗#映画母性 11/23(水・祝)公開 #戸田恵梨香 #永野芽郁#高畑淳子 #大地真央 pic.twitter.com/TELg7fyJ5W
— 映画『母性』公式 (@bosei_movie) November 16, 2022
時代設定
ちなみに『母性』では主に4つの時期に分かれて物語が展開していました。
ダイヤル式の電話、タクシーの形状、炊飯器、テレビやビデオデッキなど現在とは異なる時代の香りが感じられましたが、原作における主な時代設定はこういった形です。
- 母24歳(田所と結婚した年)
- 娘が6歳(母31歳)
- 18年前(娘が高校生)
- 2010年頃(娘が同僚と飲んでいる現代)
娘が「りっちゃん」で飲んでいる現代が「二十一世紀に入って十年経ち」と表現され、仁美との一件で家を出た田所哲史の帰還は18年前と描写されています。また映画では台風の夜から「12年後」という表現が出てくるため、田所の屋敷で暮らす時期は娘が高校3年生の年だと想定できます。
現代を2010年とし、“18年前”の娘を18歳とすると、娘の高校生時代は1992年の話であり1974年生まれ、彼女の幼少期の話は70年代終盤から1980年頃ということになります。“現代”の娘は36歳ですね。
映画では“現代”の娘も永野芽郁さんが担当したことで(36には見えなかった)、90年代前半の高校生時代からウェブサイトでニュースを閲覧する現代への唐突なジャンプアップを感じましたが、原作を鑑みると1973→1974→1980→1992→2010という流れだと思います。
プロモーションの仕方には疑問
原作との相違点について上で触れましたが、基本的に『母性』は忠実に原作を再現している映画だと思います。
小説は開始から6割程度まで映画とほぼ同様の形で進んでいました。そこから母(戸田恵梨香)に訪れる運命の差異や、存在感が希薄な男性陣の描写分量においては、改変ではなく省略という方が正しいです。
ただ映画の予告編では一つの事件に二人の証言、真実か嘘か、と相反を煽るような描かれ方がされていました。こうなるとどちらが真でどちらが偽なのかということを決めることが本筋に見えてしまいます。
もちろん、戸田恵梨香が娘を抱きしめた行動は永野芽郁の目線からすると全く別のものとして捉えられている象徴的シーンに代表されるように、この映画は対面での行動が行動者・受容者それぞれで悲しいほどにすれ違う部分が魅力ではあります。
母は実母(大地真央)の薫陶を受けて真心たっぷりの手料理レパートリーを習得したはずが、娘の中では三食丼とハンバーグの登場率がやたらと高い食卓と記憶されているのも、双方の言い分に疑念を抱かせるものでした。
小説『母性』(新潮文庫)の解説では間室道子さんにより、二大「信用できない語り手」として表現されています。
けれど、間室さんの解説でも言及されていましたが、『母性』という物語は母娘どちらが真偽なのかを探っていくのが主旨なわけではないと思うんですよね。
母と娘の関係は対立構造でもありません。母 / 娘への愛が伝わらない、誤解されてしまうという点ではむしろ類似構造なのではないでしょうか。これは小説、映画両方から感じられたことです。
今回の予告編から受けた印象は、犯人探しのようなものでした。その意味でプロモーションの仕方には疑問を感じます。
母は怪物だったのか
予告編では「母という名の怪物たち」という表現がされていました。
それは戸田恵梨香の「母」はもちろん、彼女の実母(大地真央)と義母(高畑淳子)にもかかってきますし、「母」になる娘(永野芽郁)の今後についても示唆しています。
ただやっぱり、この宣伝手法には疑問を覚える部分があります。





極端(かつしばしば胸糞)な人物ばかりが出てくる本作品ですが、「母という名の怪物」と表現するのは違うと思います。
母の愛
戸田恵梨香の「母」において、判断理由の全ては「実母(大地真央)」の存在です。実母が喜んでくれることがすなわち自分にとっての喜びかつ受容できる愛情でした。その愛を実感するために、彼女は実母の目に映る絵と同じものを見ようと、また描こうとしていきます。
田所哲史(三浦誠己)との結婚もそうでした。田所の絵を好きではなかった彼女は、実母が彼の絵を気に入っているのを知ると考え方を変えます。「母と私が同じものを見て違う思いを抱くなど、あってはならないこと」だからです。
彼女の行動理由は母が望んでいるか、否かに集約されます。そして彼女の取った行動全てを母は肯定し、賞賛し、尊んでいました。
ゆえに彼女は、相手が自分に何を望んでいるかを察し、考えた上で行動することが肝要だと考えるようになります。
ただ、その「相手」とは広いものではなくて、実母一人のことでした。「私は母の分身」といった表現がありましたが、母の存在は彼女が露木ルミ子として生きている証であり生きがいであり、全てでした。
極論すれば彼女の世界は自分と、愛を与え合う母だけで構成されていたともいえます。
母と娘
田所と結婚してからも実母との濃密な関係は続いていました。むしろ前以上に親子水いらずの関係だったとも、彼女は回顧しています。
食事に対して感想を述べず、髪型を変えても家に花を生けても新婚の田所は何も気づきませんでしたが、お母さんは褒めてくれます。
そんな幸せな時間に自分の娘という新たな存在が入ってきました。
母は喜んでくれました。娘を産み出したことで、彼女は実母からの大きな愛情に満たされていました。
ただ、娘の誕生と同時に、「お母さん」の愛情はルミ子(戸田恵梨香)が独占できるものではなくなります。
付け加えると娘が戸田恵梨香のことを「ママ」と呼んでいるのは、ルミ子が「お母さん」と言う単語を使わせなかったからです。「お母さん」はルミ子から見た実母だけです。
映画で度々描かれていた通り、ルミ子にとっての娘(落井実結子)は母に嬉しい思いをしてもらう“ため”、また自分が母と同じ絵を描く“ため”の存在でした。
母が望むことは自分が望むことと同一。なのでその逆も然りです。
ルミ子は娘に相手(おばあちゃま)が喜ぶような行動をしましょうね、と育てていきました。
平行線
しかしルミ子は最愛の実母を失いました。また、娘・清佳は無償の愛を与えてくれた祖母を失いました。
田所の実家に身を寄せることになったルミ子は、姑(高畑淳子)から痛烈ないびりを受けます。義母の耳につくのは私の立てる音ばかりだった、とはルミ子の回想です。
辛い仕打ちを受けても、彼女はここで生きていくしかありません。そのためには姑に“娘”として認められる必要がありました。
彼女は「義母の娘になろうと」姑へ心を向けていきます。
それに付随して、彼女が娘(永野芽郁)に望む行動というのも規定されていきました。行動を喜んでくれる、褒めてくれるおばあちゃまはもういません。できるのは田所の屋敷で自分たちが生きていけるように、波風を立てないということです。
だから娘・清佳にとっての「愛される」とは「許される」とイコールでした。
けれど、彼女が傷ついたママを意地悪なおばあちゃんから守ろうとする行動(母への母性)は、往々にして裏目に出ます。
ママが望んでいることだと思ったのに。許されません。愛されません。





ちなみに映画の「母性」はタイトルの出し方が特徴的に思えました。
「母」という漢字の書き順は上の動画のように、1画目は平仮名の「く」のような形で左辺〜下辺を、2画目で上と右辺を書き、まず四角の囲みを作ります。
続いてその中に二つの点を打ち、最後に真ん中の横棒を通します。
けれど、この映画のタイトルでは違いました。
1画目で左辺の縦棒だけ、2画目は右辺の縦棒だけを書き、その後で3本の横線と真ん中の点々を通していきます。
「性」も本来の書き順とは異なり、縦棒、横棒のそれぞれ平行する部分から書いていきます。
戸田恵梨香と永野芽郁の悲しくなるほどのすれ違いが見どころの映画ですが、あのタイトルは交錯せずに平行線をたどる二人の“母性”を示す意味もあるのではないかと個人的には解釈しています。
母への依存
映画の予告編で登場した「母という名の怪物たち」というフレーズに、違和感があると書きました。
「愛能う限り、大切に」育ててきたルミ子(戸田恵梨香)の母性は、娘・清佳には違う形で映り、決してポジティブには見えません。
そのルミ子を愛能う限り大切に育ててきた実母(大地真央)の愛情も、ある視点からは箱入り娘を形成した過度な保護に映ります。
実の娘と嫁を徹底的に差別する高畑淳子も、不愉快極まりない(ルミ子にとっての)義母に感じます。





小説『母性』(新潮文庫)の巻末解説を引用します。
手近な辞書で「母」(ぼ)を調べてみると、【①はは。「—子・—胎・—乳」「祖—・父—」②根拠地。出身地。「—校・—港」③物を生み出す元になるもの。「—音・—型」「酵—」④母のような役割を担うもの。「聖—・寮—」】と、いいことがいっぱい書いてある。一方「父」(ふ)を見ると、【①ちち。「—子。—母」②年老いた男性。「漁—」】……え、これだけ⁈
あの台風の夜、究極の選択を突きつけられたのだ、と物語後半、妻である<私>に激白された夫(つまり<わたし>の父親)が放った一言には、もう、“さすが「父」(ふ)だ!”とある意味感心。長いこと家長制度とか男尊女卑とか、「父親上等」であった日本だが、分数は「分父」ではなく、国は「父国」ではない。表立って男たちが力を振るってきた長い社会が、「母」に期待し、甘え、後始末を押しつけてきたものは、とてつもなく大きいのだ。
“母という名の怪物たち”とは、こちらの解説の通り、「母」への期待、依存が表面化させたものではないでしょうか。
では、“父という名”を与えられた男性陣はどうだったでしょう。
妻と向き合うことをやめて仁美さんの元に逃避した田所哲史は、またその田所が少年だった頃に暴力で抑圧していた田所の父には“怪物”の要素はないのでしょうか。





「それでも母親か!」は高畑淳子が放った一言ですが、「母親」はこうあるべき、という通説の持つ重荷がこの映画からは伝わってきます。子どもに与える影響力についても同様です。
私がこの先の人生で誰かの「親」になるのかはわかりませんが、ちゃんと親になれるのだろうか?無償の愛を与えることができるのか?子どもと分かりあうことができるのか?と、『母性』を観て不安になりました。自分が戸田恵梨香のルミ子には絶対にならない!という自信はありません。
「毒親」という言葉や「親ガチャ」という言葉も一般化した昨今ですが、この映画では母子間に愛(母性)が当然あるとされることや、その母性への無責任な期待がのしかかります。少なくとも私は、この映画の母たちを怪物と表現することはできませんね…。
一緒に鑑賞した方は「娘(永野芽郁)はいい子だと思ったけど誰にも感情移入できなかった。胸糞だった」と言っていました。確かに気が滅入るようなことがたくさん出てくる作品だったと思います。
ただ個人的には原作から起伏を取捨選択しつつ、「母性」への捉え方を投げかける良い映画でした。戸田恵梨香さんや永野芽郁さんの魅力を引き出したという点でも素晴らしかったです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
小説は映画にない展開もあるので興味ある方はご覧ください!
こんな映画もおすすめ
白ゆき姫殺人事件
Amazon Prime Video
U-NEXT
Netflix
エイプリルフールズ