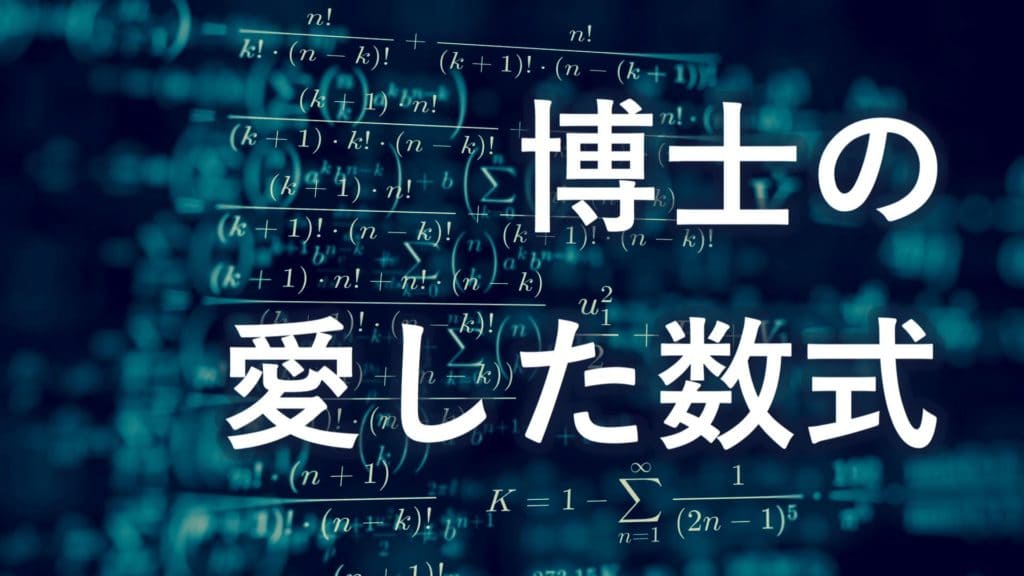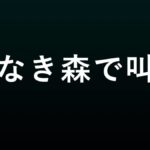こんにちは。織田です。
2006年に公開された映画『博士の愛した数式』を再鑑賞しました。
2003年に小川洋子の原作小説が刊行され、2005年に文庫化、翌年1月に実写映画の公開と、計画的なメディアミックスが施された作品です。
ベストセラーとなった小説は文庫版で2006年に読了、映画もDVDで2010年に鑑賞していましたが、久しぶりに再鑑賞してみました。
『博士の愛した数式』のスタッフ、キャスト
監督・脚本:小泉堯史
原作:小川洋子
博士:寺尾聰
家政婦の杏子:深津絵里
ルート(幼少時):齋藤隆成
博士の義姉:浅丘ルリ子
ルート(成人時):吉岡秀隆
あらすじ紹介
元大学教授の数学者(寺尾聰)の家に派遣された家政婦の杏子(深津絵里)は、彼が交通事故の後遺症で80分しか記憶がもたないことを告げられる。戸惑う杏子だが、ある日、彼女の息子(齋藤隆成)と数学者が会い……。
MIHOシネマさんの記事でもネタバレありのあらすじ解説がなされています。
興味のある方はこちらもどうぞ。
以下、感想部分で作品のネタバレや展開に触れていきます。未見の方はご注意ください。
映画のネタバレ感想
以下、作品のネタバレや展開に触れていきます。未見の方はご注意ください。
大人になったルート少年
記憶能力に制限がある博士(寺尾聰)と、その博士のもとで働く家政婦(深津絵里)。
作品の大前提はここです。
また本記事では深津絵里が演じる家政婦・杏子を「私」と表記させていただきます。理由は後述します。
「私」(母親=深津絵里)の視点で書かれた原作に対し、映画では彼女の息子「ルート」(吉岡秀隆)が数学教師になり、教え子たちに博士と過ごした述懐する形式を取っています。この「ルート」とは彼が幼少時に博士からつけてもらった呼び名です。
時間軸としては吉岡秀隆版ルートがエピソードを生徒の前で話し始め、彼の幼少期に回想シーンが移り、エピソードが一区切りするたびに、時間設定が教室のルート先生の元に帰ってくる形です。
また博士の話した数式や数学用語を、ルート先生が丁寧に説明するところもこの作品のポイントとなっています。


ルートと呼ばれて19年。
そう話す先生の言葉からは、博士に与えてもらったルートという愛称を大事にしながら生きてきた彼の優しさ、人間性がにじみ出ています。
語り手を務めるものの、吉岡秀隆が出てくるシーンの総時間はそこまで多いものではありません。
が、大人になったルート少年を優しいストーリーテラーとして起用したのは間違いなくこの映画の勝利です。
記憶をなくした博士と
博士は記憶が80分しか持たないため、恒常的に覚えておかなければならないことをメモに書きつけ、上着に貼っていきます。
どうしてメモを上着に貼り付けているのかの理由づけは小説では叙述されているものの、映画ではほとんどなされていません。
見ればわかるでしょうということで省いたのか、原作を知っている前提がゆえに省いたのかは図りかねますが、潔いくらいにバッサリと削られています。
この理由づけの省略は初回鑑賞時も今回も意外に感じた点でしたが、この作品は博士の限定的な記憶が悲観的に描かれることはほぼありません。
これは渡辺謙がアルツハイマー病を患った『明日の記憶』とは大きく異なる部分でした。
「私」(深津絵里)もルートも博士の記憶能力を受け入れて、何度も何度も「はじめまして」を繰り返していきました。
記憶のできない博士に対してルートが無邪気に傷つけることもあるのでは?とヒヤヒヤしていましたが杞憂でした。
ルートはありのままの博士を受け入れる優しくて頭の良い男の子でした。
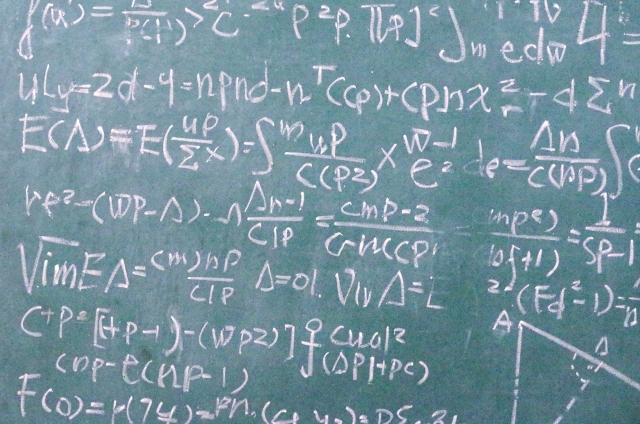
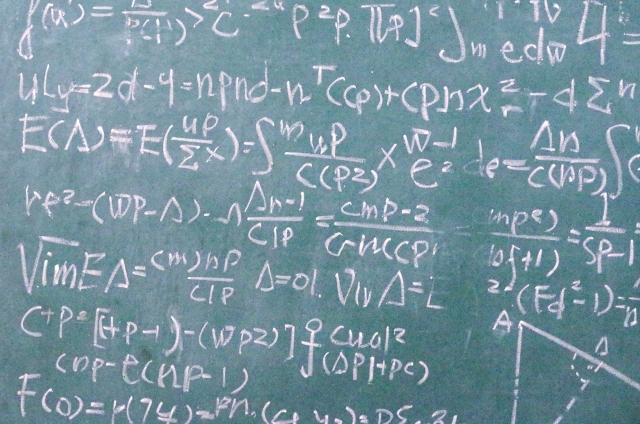
また、この映画では人の固有名詞がほぼ出てきません。
深津絵里が演じた「私」は自分のことを「家政婦です」と博士に名乗り、息子のことも博士の前では一貫して「ルート」と呼び続けます。
未亡人の義姉(浅丘ルリ子)が唯一「私」のことを「杏子さん」と本名で呼ぶシーンがありましたが、基本的に深津絵里は自分のことを「私」と呼び、博士からは「君」、ルートからは「お母さん」と呼ばれます。
だから本作品において深津絵里の役名が「杏子さん」であることにそれほど意味はありません。博士とルート、義姉については名前が明かされることすらありません。
なぜかといえば、それはおそらく博士が数字を通して事情を把握する人間であり、そこに名前という記号はあまり意味がないからだと思います。
博士にとって「私」は「足のサイズが24センチで2月20日生まれ」の家政婦さんであり、ルートは「平方根のような平べったい頭頂部になかなか賢い心が詰まってそうな少年」でありました。
小説版の「ちょっとすまないが、君」という博士の口癖は再現されない一方で、博士が非数学の記号から数学化し続ける言葉たちは、「私」の記憶に刻まれていき、「私」が数字に興味を抱くきっかけになりました。とっても美しい博士からの授業だと思います。
博士の愛した江夏
博士はルートと同じく阪神タイガースが好きで、とりわけ28番の江夏が大好きでした。
防御率、勝利数など元気な頃に覚えていた記憶は忘れていない一方で、その後の現代(作品内の当時)のことはわからないため、博士にとってのタイガースはエース江夏の時代・1960年後半から70年台前半の記憶で止まっています。
博士の愛した江夏は南海にトレードされ、すでに現役を引退していました。
FAやポスティング制度が確立された現代ではあまり例を見ない形ではあるものの、浦島太郎状態になってしまった博士が混乱をきたしてショックを感じてしまうのは仕方ないことでしょう。
ここは博士の記憶能力による悲しい出来事の、数少ない事例の一つでした。
心を痛めた博士に対し、「私」は息子・ルートが所属する少年野球チーム「タイガース」の背番号を博士が好きだった往年のタイガースのものにすることを思いつきました。
村山実、田淵、川藤。「江夏の28番がいないぞ」と困惑する博士に「私」は「28番は博士のためにとっておきました」と笑いかけます。
ルートの背番号を「√」にしたことも含め、「私」の優しさが凝縮されたシーンであり、その優しさが博士に伝わったことが嬉しくてたまりません。
博士を愛した人たち
博士も「私」もルートも、本作の登場人物は素直で優しい気持ちの持ち主ばかりでした。
実際は博士に対して可哀想だとか偏屈だとか、そういった思いを持つ人だっているはずだし、描けたはずです。
それでも上で述べたように、「私」もルートも博士との度重なる「初めまして=ゼロとしての対面」を繰り返すことを厭わず、博士の愛した数字たちとの出会いを受け入れ、純粋な博士を愛しました。
そして普段の日常を、数字という要素を取り込みながら博士と一緒に楽しみました。
友愛数や階乗、自然数などたくさんの数字を教えてくれた博士。
ネピア数「e」、虚数「i」、円周率「π」という無理数。e(iπ)+1=0。この美しく秩序をもたらした数式こそが博士の愛した数式。
数学はおろか、算数ですらダメダメだった僕も、本書を読み映画を観た後は数字への印象が一変しました。
ゼロ(無)というものは何もないまっさらなものという意味だけではなく、カオスな多々を秩序立てて統一するもの。
無である一方で、無がなければ調和を作り出すことなんてできないと知れたことは教訓になりました。
この映画には悲観的な山場や感動的な山場が盛り込まれてるわけではありません。
それでもこの作品を勧めたいのは新しいことを発見する楽しさと、数字の織り成す美しい秩序と、人間の優しさがぎゅっと詰め込まれているからです。
「君には息子がいるのか?」
「素晴らしいと思わないか?」
「実にチャーミングな数字だ」
寺尾聰の演じる博士が話す美しい定型文たちは、きっと癖になるはずです。
時間が経っても見返したい映画の一つですね。大好きです。