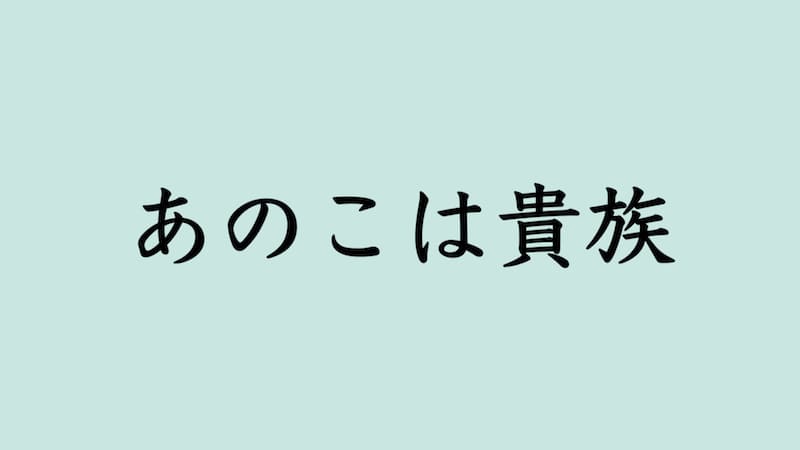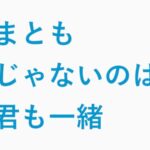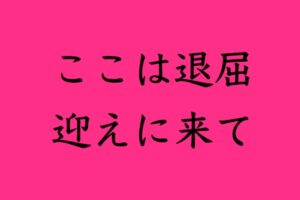こんにちは。織田です。
今回は2021年公開『あのこは貴族』をご紹介します。
岨手由貴子監督。原作は山内マリコさん。門脇麦さんや、水原希子さんが出演しています。
非常に評判が良かったので結構ハードル上げて鑑賞に臨んだんですが……素晴らしすぎましたね。ちょっとレベルが違いました。ここ何年かで一番。
大好きな、忘れられない映画になりました。
日本における女性のあり方とか、階層の格差とか、色々なものを丁寧に、かつ公平に描いた映画だと思うし、特に「東京」と、東京で生きる人たちを映し出した最高の東京映画だと感じました。
登場人物たちが紡ぐ言葉も、心にしっとりと、ずっしりと染み渡る素晴らしいものばかりでした。いや、何回も泣いた。





あらすじ紹介
都会に生まれ、結婚こそが幸せという価値観を抱く20代後半の榛原華子(門脇麦)は、結婚を意識していた恋人に振られてしまう。名門女子校時代の同級生たちの結婚や出産を知って焦る彼女は相手探しに奔走し、良家出身で容姿端麗な弁護士・青木との結婚が決まる。一方の時岡美紀(水原希子)は富山から上京して慶應大学に進むものの中退、働いていてもやりがいを感じられず、恋人もおらず、東京で暮らす理由を見いだせずにいた。全く異なる生き方をしていた2人の人生が、思わぬ形で交わっていく。
スタッフ、キャスト
| 監督・脚本 | 岨手由貴子 |
| 原作 | 山内マリコ |
| 榛原華子 | 門脇麦 |
| 時岡美紀 | 水原希子 |
| 青木幸一郎 | 高良健吾 |
| 相良逸子 | 石橋静河 |
| 平田里英 | 山下リオ |
| 華子の長姉 | 石橋けい |
| 華子の次姉 | 篠原ゆき子 |
| 長姉の夫 | 山中崇 |
| 幸一郎の母 | 高橋ひとみ |
華子(門脇麦)は東京の名家・榛原家の三女。上の姉2人(石橋けい、篠原ゆき子)は少し歳が離れています。
逸子(石橋静河)は華子の同級生。小学生から華子と同じ女子校に通い、育った環境も似ています。
一方で、美紀(水原希子)と里英(山下リオ)は富山から慶應義塾大学に合格して上京。その後、美紀は東京で、里英は富山に戻って社会人生活を送っています。


『あのこは貴族』の作品情報については、MIHOシネマさんの記事であらすじ・感想・評判などがネタバレなしで紹介されています。映画未見の方はぜひ予習にどうぞ!
東京の中の特別な東京
東京のセレブタウンと聞くと、どういうところを想像するでしょうか?
白金、麻布、自由が丘、ニコタマ、田園調布、豊洲、月島、勝どき……
タワーマンションを連想する方も多いかもしれません。
『あのこは貴族』の主人公・榛原華子(門脇麦)は渋谷の松濤(しょうとう)で暮らす名家の三女。お父さんは整形外科の開業医です。
#門脇麦 榛原華子
上流家庭に生まれ、三人姉妹の末っ子として
何不自由なく育てられた華子東京の限られたエリアの中で「結婚=幸せ」と疑わずに育ったが、20代後半ではじめて焦りに直面している。#あのこは貴族 pic.twitter.com/DS1ptbomnJ
— 【公式】映画『あのこは貴族』 (@aristocrats0226) January 12, 2021
この松濤は有数の高級住宅街で、政治家、芸能人、実業家といった高所得者が多く暮らしている街。高所得者層といっても、そんじゃそこらの富裕層じゃ住めないレベルです。
そんな超一等地に榛原家は代々住み続けてきました。
「東横線とか田園都市線って、ミーハーな人が住んでそう」
相楽さんはなんの気なしにそんなことを言う。
(中略)
東京の街には、しきたりと常識がないまぜになったような共通認識が張り巡らされていて、それは代々ここに住みつづけている人たちに、脈々と共有されていた。最近になって外部からやって来ては、踏み荒らすように西へ西へと住む場所を押し広げていった人たちとは、見えない壁で隔てられている。けれどもそのことをあからさまに口にするのは品がないからとはばかられ、あまりおおっぴらに俎上にのせることはなかった。しかしだからこそ、この手の話は面白かった。
同級生の相良逸子(石橋静河)は原作小説内で、土着の東京人と他の土地からやってきた富裕層をナチュラルに区別しています。その意味で言うと、華子も逸子も、また港区の神谷町(東京タワーの近くですね)に豪邸を構える青木家(幸一郎=高良健吾の実家)も、「東京の生粋の富裕層」なわけです。
華子たちが言う「東京の人」
#石橋静河 相楽逸子
自立した世界観を持つ
ヴァイオリニスト・逸子華子の良き相談相手。
華子と美紀を引き合わすことになる。#あのこは貴族 pic.twitter.com/IeFGQPtqQh— 【公式】映画『あのこは貴族』 (@aristocrats0226) January 15, 2021
「華子は絶対、東京の人がいいと思っていたんだ」
「松濤で生まれて東京の外から入ってこれないような所で生きてきたんだから」
逸子(石橋静河)は、幸一郎(高良健吾)との縁談が順調に進む華子(門脇麦)にこう諭しました。
先ほど紹介した原作小説の一節でもあった通り、逸子たちの世界は「東京の人」と「それ以外」に区分されています。
そしてここで挙げられている「東京の人」とは、東京の”良いところ”に代々住み続ける方のことです。
東京都民1400万人、そのうち東京23区住民968万人の中の、ごくごくごくごく一部の方たちを指しています。





「第1章」のタイトルは「東京 とりわけその中心の、とある階層」。
言い得て妙です。本当その通り。
「とある階層」の普通
華子たちは電車に乗りません。
移動は基本タクシー。元日には家族で帝国ホテルに集まって会食をして高級食材に舌鼓を打ち、毛皮の話をしたり、家族写真を撮影したりします。お盆には和服姿でうな重の出前を食べています。
一方プライベートではお母さんと連れ立って美術館や百貨店の展示に行ったり、ホテルのレストランでアフタヌーンティーを嗜んだり。ガツガツすることも強欲に買い物することもなく、のんびりと、おっとりと地に足をつけて生活してきました。
華子や逸子同様、慶應に幼稚舎から通っていた幸一郎も同じ部類です。
そんな“内部生”について原作ではこのように紹介されていました。
〝いいとこの子〟には二種類ある。強欲でワガママで、お高くとまった下品な金持ちというイメージは、一代で財を築いた成金特有のもので、慶應にいるお金持ちは、何世代も続く裕福な家に生まれたタイプが多かった。彼らはむしろおっとり育てられ、ガツガツしたところがまるでない。東京が地元で、実家から大学へのんびり通ってくる。お金があると心にまで余裕があるみたいだ。
自分の学生時代を思い出すと、慶應じゃなくても大学にはこういう環境で育った学生がいて、その子たちは煌びやかに着飾ることも夜遊びに明け暮れることもありませんでした。ユニクロとかも普通に着ていました。ただし、佇まいや行動に漂う余裕、慌てなさ。
新鮮でした。「お金持ち」への考え方が変わりました。
華子も逸子も幸一郎も、そんなカテゴリーの人たちです。
差異に気づくひとたち


映画内で美紀が帰省に利用していた「あいの風富山鉄道」。2018年撮影
「東京の、とりわけその中心の、とある階層」が優雅におっとりと、地に足を着けて生きている一方、この映画では時岡美紀(水原希子)、平田里英(山下リオ)という富山から上京した二人にもスポットを当てます。美紀の地元は魚津というホタルイカや蜃気楼が有名な港町です。
二人は同じ高校から慶應義塾大学に進学。幸一郎(高良健吾)の同窓生となりました。慶應に(少なくとも)二人合格者を出すくらいですから富山県内の進学校であることは予想がつきます。入学式で美紀が「平田さん」と呼んでいたことから、二人は高校時代それほど親しい間柄ではなかったこともわかりますね。
華子(門脇麦)や逸子(石橋静河)が強烈なためコントラストが際立ちますけど、美紀も里英も富裕層の対極(貧困層)ではありません。
お父さんの失業により慶應を中退せざるを得なかった事情はあったにせよ、美紀は何とか東京を生き抜き、現在では狭いながらも東京タワーのよく見える物件に住んでいます。二分するのであれば成功者と言って差し支えないと思います。
親からの援助が途絶えて大学中退を余儀なくされたという点では中村蒼主演の『東京難民』もそうですね。こちらはより明確に社会の格差を描いています。
区分、分断、逸脱
そんな里英と美紀は慶應で「心にまで余裕があるような」内部生を目の当たりにし、セカイの分断を実感します。10年以上経った現在では華子や逸子と出会い、ナチュラルに生育環境の違いを表す彼女たちに少々面食らいます。
美紀が「ダサいんだけど割れずに生き残っている手馴染みの良いマグカップ」の話を振っても、華子にはピンと来ていません。
華子は華子で、箱入り娘から外に出ようとしたところで、様々なここではないセカイを痛感します。
初等部からの仲良しグループでは華子と逸子だけが未婚で、新年早々のお茶会では未婚組、既婚組と2対3に分断されていますし、美紀たちが生きる為に必死こいて食い扶持を探している中でも、華子は働いていいかどうかすら、自分に決定権がないわけです。
逸子ちゃんは、華子と同じようでありながら、「経済的にも精神的にも自立していたいし、いつでも別れられる自分でありたい」存在です。名前が表しているのかはよくわかりませんが、凝り固まったセカイの常識から逸れて生きていたいと思う人です。





だから仲良しグループの中でも、あの子結婚興味あるのかなとか、仕事だけでやっていけないから日本戻ってくるんでしょとか、悪口ギリギリのことを言われてしまいます。“私たちとは少し違うから”による無意識的な区別ですね。
里英の「このこたち貴族」以外にもこの映画では様々な差異が描かれていて、「持つか持たざるか」になるとその差異は格差として印象付けられていきました。
嫌味のなさが唸らせる
ただしこの映画が上手いのは、「とある階層」と「そうでない階層」の差異を映し出したときに、「とある階層」側の行動に嫌味がないんですよね。





例えば美紀(水原希子)たちは持たざる者であり、とある階層へ至らない者であり、多分観ている人の多くも彼女たち側の視点で見ることが多いとは思います。
『あのこは貴族』の美紀たちは「地方」という文脈で、上京したことがある人にとっては彼女たちのルーツと重ね合わせるようにしてもちろん刺さりまくるでしょうし、地方との対立軸として見られがちだった、東京を地元とする人たちにも「こっちの階層」側として響くんじゃないかなって思うんです。


里英(山下リオ)が酒かと思ったと述懐した4200円のアフタヌーンティーは大学生がそうそう気軽に嗜めるものでもないですし、華子(門脇麦)がドン引きしていた、騒がしくてトイレの汚い大衆居酒屋(神保町・酔の助)のほうが心地良いじゃんって思う人もたくさんいるはずです。
でもだからと言って、「そうじゃない」側の世界に対して嫌悪感とかヤッカミとかが介入してこないんですよ。あまりにもセカイの違いがナチュラルすぎて。
感情を持った「分断」を描いていたのって、次姉・麻友子(篠原ゆき子)のセッティングで出会った亀井という男が華子に言い放った「家事手伝いって何?」くらいじゃないでしょうか。
ユニクロ?そりゃ行くわよ
2020年公開の『空に住む』は主人公(多部未華子)の住む(渋谷近辺と思われる)タワマンが舞台になっていて、そこでは「とある階層」側の華やかさや息苦しさが強調していました。
個人的には多部未華子の叔母さん(ミムラ)の、承認願望が服着て歩いているようなキャラクターが本当に無理だったんですけど、ああ息苦しいなこのセカイ(階層)っていう風に感情を植えつけられたんですよね。
この人らはマックとかしまむらとかサイゼとかユニクロとか死んでも行かないだろうなと思ったんですよ。
もちろんそこには自分がその層にたどり着いていないコンプレックスがあります。
『あのこは貴族』の榛原一家もマックやサイゼには行かないと思います。でもこの映画を観ていると「そりゃ行かないよね」って納得できるんです。そこに妬ましいだの世界が狭くて息苦しそうだの、そういう感情は介在しませんでした。だってそりゃあね、って。
先ほど引用した原作の言葉を使うならば「ガツガツしたところがまるでない」。


東京駅
アフタヌーンティー4200円を当たり前のように注文し、「ここ久しぶりだよね」「こないだはマンダリン(マンダリン オリエンタル 東京)だったよね」と異世界の言語を使う慶應時代の美紀たちの同級生にも、実家にクリスマスツリーを飾ったことがないという美紀に「信じられない」と目を剥いた華子にも、全く他意や嫌味を感じません。
「野蛮」「ユニクロ“なんか”行くの?」と刺激的な言葉が飛び交った序盤の榛原家会食シーンでさえもそうです。
仮定の話ですが、もし慶應のあの子たちと美紀、里英がバイトの話をしていようものなら、「何でバイトなんかするの?」という話になったかもしれませんけど、『あのこは貴族』において所得差の直接的な描写はありません。
だから、富裕層とそうでない層を描いた物語にありがちな、あんたたちには一生わからないだろうけどね!的な分断がないと思うんですよね。
『あのこは貴族』は、決して差異を自覚して分断を促す映画じゃありません。
狭いセカイへの理解
さらに言えば華子たち富裕層のセカイは、一見対極構造にある美紀の地元・富山のコミュニティとも共通しています。
「落下傘部隊のように」次々と結婚していく周囲の女性。でも私たちってそう育てられてきたでしょう?な華子たち。
女とは〜論を父親世代から押し付けられ、「定年後最大の不幸が娘が結婚しないこと」と言われる里英や美紀たち。
「本当に子供が産める年齢で結婚できるのかしら」と母親に言われる華子。


落下傘部隊
限定的かつ身の丈にあった東京だけをタクシー移動ですくい取り、facebookのお友達も同族ばかりで固められる華子たち。
かたや富山ではスポーツカーを先パイに譲ってもらった美紀の弟や、浜崎あゆみのSEASONS(2000年リリース)が流れる高校の同窓会でアップデートに乏しいイキり方をする同級生の男。ココこそが世界と信じてやまない私たちの場所。
「うちの地元だって町から出ないと親の人生トレースしてるだけだよ。そっちの世界とうちの地元ってなんか似てるね」
人生の進むべきレールがあらかじめ敷かれている華子に対して美紀はこう言うわけですが、「そっちの世界」の最たる例は幸一郎(高良健吾)でしょう。華子の義兄(山中崇)は幸一郎が地盤を継ぐことは子供の頃から決まっていて、華子との間に男の子が生まれればその子が跡継ぎとなるだろうと話します。
富山は富山で、今までそれで恥をかいてきたこともないであろうイキり型の男性(石井くんといったかな)が土建屋の三代目になって地元の有力者になっているわけです。
幸一郎にとっての将来は夢とかじゃなくて義務に近いものですし、描かれてはいないけど土建屋の息子くんもそうなのかもしれません。
原作小説を読んだ感じではもう少し幸一郎を、女性側から共通のエネミーとして捉えた印象がありましたが、映画においてはそこまで幸一郎に対して感情的になることがなかったんですよ。
中立的に、公平にというのはここが一番大きい。小説以上に、映画は感情的な分断を撤廃していた気がします。差異を描いていながらも。


差異を嗤うわけでも境遇に諦めるわけでもなく、美紀は華子に語りかけます。
「どこで生まれたって、最高って日もあれば泣きたくなるような日もあるよ」と。
個人的に同窓会で使われた浜崎あゆみのSEASONSには、2001年高校卒業世代の時代補強だけにとどまらない作品へのシンパシーを感じましたね。





東京のリアルがそこに
最後に「東京映画」としての感想です。
「みんなの憧れでつくられていくまぼろしの東京」というセリフがありましたが、『あのこは貴族』で描かれる東京の景色は、そんなに憧れの詰まったキラキラしたものでも、落とし穴が大きな口を開けて待っているドロドロしたものでもないと思います。
渋谷、新宿、池袋、上野。そういった人が多く集うところ=東京っていう図式ではないんですよね。
カオスをかたどっていく群衆はこの映画において意味を持ちません。
そういう場所ってもう「わかりやすく東京なところ」のアイコンじゃないんですよね。


渋谷。2019年
大手町や東京駅。内幸町。華子が乗るタクシーの車窓に流れていく東京は、文字通りの背景でした。
無機質でどこにでもありそうながらも、全ての人を分け隔てなく平等に、適度な距離感を持って受け入れる都市。
見慣れた景色。工事のクレーンが空に伸び、刻一刻と姿かたちを変えていく都市。
この街は自分にも居心地が良い
原作者で富山出身の山内マリコさんは「FRAU」への寄稿でこのように綴っています。
日常的な生活は、車にあれこれ詰め込める地方暮らしのほうが圧倒的に便利だけど、それとは別次元の居心地のよさにおいて、東京はぶっちぎりなのだ。
ああ、ここにいていいんだと、街から許容されている感じ。街自体が巨大すぎるゆえ、「あんたのことまで見てられないから、好きにして」と放っておかれている感じが東京にはある。
これは神奈川や埼玉、千葉の方には共感していただけるかもしれませんが、神奈川で生まれ育ち、就職を機に都内に住んだ自分は「上京」っていう感覚を経験したことがありません。
行こうと思えばそんなに時間もお金もかけずに行けた東京は、覚悟を抱いて向かう場所じゃないし、地元横浜はわざわざ覚悟を決めて帰る場所ではない。





でも、東京という都市はそんな中途半端野郎がフラフラと彷徨っていても、干渉されることなんてありません。自由です。
#水原希子 時岡美紀
富山に生まれ、
ごく普通の家庭で育った美紀猛勉強して入った大学を家庭の事情で中退したことに挫折感を抱えている。
年に1度帰省しては、数日で東京に逃げ帰ることをもう何年も繰り返している。#あのこは貴族 pic.twitter.com/bkgrfrtkkd— 【公式】映画『あのこは貴族』 (@aristocrats0226) January 13, 2021
「年に1度帰省しては、数日で東京に逃げ帰ることをもう何年も繰り返している。」とある通り、きっと美紀にとっても東京は息苦しくも帰る場所になってるんですよね。
僕にとっても「東京」は居心地が良いです。だから無機質で冷淡な背景も、それでも確かにこれこそ東京だよねと馴染み深く映りました。ああ、いつの間にか自分もこの街の一員になっていてこの街が好きになっていたんだ。そんなことに気づかせてくれる映画でもありました。
東京って息のつまる魔窟かもしれないけれど、でもその魔窟は誰もを許容し、ここで生きていくことを認めてくれる都市なんじゃないかなと思います。縛られたものから勇気を出して自立する人たち。この映画ではそれが華子であり、美紀だったりするわけですけど、きっと映画を見た人たちをも、受け入れてくれる。
そんな東京を、そして東京に翻弄されながらも東京を形づくり育てていく人たちを、中立的に優しく映し出した『あのこは貴族』は、史上最高の東京映画でした。
素晴らしすぎました。ありがとうございました。
山内マリコさんの原作もおすすめです!刺さり方はきっと映画以上。
こんな映画もおすすめ
ここは退屈迎えに来て
夜空はいつでも最高密度の青色だ
ほしのふるまち
最後までお読みいただき、ありがとうございました。