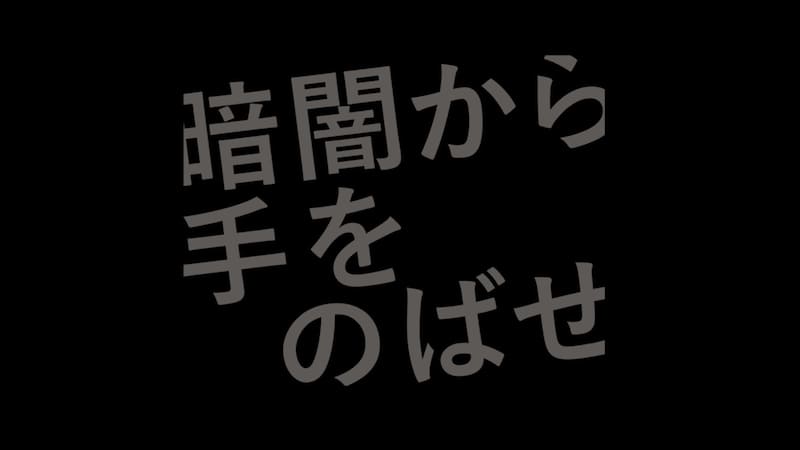こんにちは。織田です。
2013年の映画『暗闇から手をのばせ』を鑑賞しました。
障がい者専門のデリヘル嬢・沙織を『リバースエッジ 大川端探偵社』などに出演した小泉麻耶が演じています。監督は長編映画デビュー作となった戸田幸宏監督。
主人公の沙織と障がいを持つお客さんたちの触れ合いを、ドキュメンタリー風に映している作品です。
『暗闇から手をのばせ』のスタッフ、キャスト
監督・脚本:戸田幸宏
沙織:小泉麻耶
津田:津田寛治
健司:森山晶之
中嶋:ホーキング青山
小西:モロ師岡
水谷:管勇毅
恐らくこの映画で最も経験豊富な役者として出演している津田寛治は、デリヘル店長の津田という役名で登場します。俳優名と役名が一緒って良いですよね。
あらすじ紹介
沙織(小泉麻耶)は、そんなに大変ではないだろうという単純な理由で、障がい者専門の派遣型風俗店ハニーリップで働くことを決める。出勤初日、彼女は店長(津田寛治)がハンドルを握る車で落ち着いたたたずまいの住宅地へと向かう。そこで彼女を待っていたのは、全身に見事なタトゥーを入れた34歳の進行性筋ジストロフィー患者の水谷(管勇毅)だった。
通常形態のデリヘル勤めの経験があった沙織ですが、上述の通り、「仕事が大変ではないだろう」という目論見のもと、津田(津田寛治)が店長を務める障がい者専門のデリヘルで働くことを決めました。
そこで出会ったお客さんたちを通じて、沙織が「健常者と障がい者」「普通とは何か」といったことを彼女なりに考えていきます。第23回ゆうばり国際ファンタスティック映画祭のオフシアター・コンペティション部門でグランプリを受賞した作品です。
以下、感想部分で作品のネタバレや展開に触れていきます。未見の方はご注意ください。
映画のネタバレ感想
以下、作品のネタバレや展開に触れていきます。未見の方はご注意ください。
媚びない小泉麻耶
デリヘル嬢を呼ぶお客さんたちは障がいを持っているため、ベッドへの移動を沙織や津田が手伝うシーンが描かれます。
とはいえ沙織たちは介護サービスではなくて風俗サービスなので、お客さんの男たちもそれなりにカッコをつけて彼女を迎え入れます。
彼らにとって沙織は大切な時間とお金を費やして迎えた女性ですが、そこに嬢と客以上の関係性はありません。
自分のこれまでを話すおしゃべりな中嶋(ホーキング青山)のような客もいれば、全く言葉を発そうとしない健司(森山晶之)のような客もいます。
それに対して沙織は淡々と聞き、淡々と仕事を進めていきます。
もちろん嬢によってはお客さんに甘えたり、媚びを売ったりして気に入ってもらおうとする子もいるはずです。けれど、沙織はそうではありませんでした。
彼女はあくまでもお金を稼ぐためにこの仕事をしているわけだし、そこでそれ以上のお金を稼ぐために(店の規則を破って)必要以上のサービスに媚びることもありません。
沙織の表情やセリフからは、障がい者をかわいそうと思ったり、健常者と区別したりということが全くありません。
これは作り手側が仏頂面の沙織を通じて込めたメッセージだと思います。
正直なところ、小泉麻耶の役どころは鑑賞前の予想と大きく違いました。
そして、感情をあらわにしない、抑揚のない声で振る舞う小泉麻耶の起用は大正解だったと思います。
小泉麻耶の沙織が没個性的な主人公になったからこそ、「(障がい者と対比しての)普通って何?」というテーマに観る側が真っ直ぐ向き合える作品になったのではないでしょうか。
喫煙シーンに見られる主導権の変化
蛇足ですが、喫煙を用いて立場が逆転する面白いシーンがありましたので紹介させていただきます。
最初のお客さん(管勇毅)のもとに向かっている車内で、助手席の沙織はタバコを吸います。運転席には店長の津田。
初出勤でこれです。媚びません。緊張も気持ちの高ぶりもそこにはありません。据わった瞳で気だるそうにタバコをふかします。
運転席の津田はそれに対して煙たそうに手を振りました。
この冒頭のシーンだけ見ると津田は嫌煙家のように見えます。
しかし、後に沙織が独断で健司の家に行き、彼の友人に喧嘩を売った(勝手にお客さんのプライベートに踏み込むことは、店側からすると当然良いことではありません)あとは、津田が運転席でタバコを吸い、(あまり申し訳なくなさそうに)謝る沙織に向かって煙を吹きかけます。
「これから働いてくれる嬢」から「雇ってもらっている嬢」へと津田にとっての沙織の立場が変化したシーンだと思います。
津田がその場において明らかに主導権を握っている様子が、タバコを通じて描かれていて印象に残る場面でした。
障がいを持っていようが「ただの客」
上述した中嶋(ホーキング青山)は、沙織と最も積極的にコミュニケーションを取るキャラクターでした。
彼の持つ障がいの種類はもちろん、「障がい者ってそもそもかわいそうなのか?」というところも沙織にあっさりと話していきます。「本番してよ〜」という一言を挟みながら。
主に中嶋、健司、水谷(管勇毅)の3人の客にフォーカスしながらストーリーは進んでいきましたが、カメラの映し方もあって彼らの話しぶりは“演じている感”が希薄でした。
これは迫真の演技かそうでないかとか、巧拙の話ではありません。
カメラに向かって現実を伝える男たち。この記事の冒頭で本作をドキュメンタリー風と評した理由です。
そしてカメラだったりインタビュアーの役割を担うのは、彼らに同情も反論もせず淡々と聞く沙織です。
また障がい者を対象とした風俗業を始めるにあたって、津田は「社会に出られずに家に閉じこもってしまっている障がい者がたくさんいる」と話しました。
家にいる→デリヘルの需要がある、しかも顧客ターゲットを絞ることで競合も少ないという、基本的かつロジカルなビジネス感覚です。
そこに障がい者「だから」という強調記号はなく、在宅男性の中で障がいを持っている人というターゲットを見つけただけにすぎません。
需要があれば「受験生専門デリヘル」でも「自宅警備員専門デリヘル」でも良いわけです。もちろんデリバリーするのはヘルスじゃなくても良いわけです。
その中で津田が一番ビジネスの可能性を感じたのが障がい者専門デリヘルだったというだけですね。
障がい者へのバイアスや、障がいを持っているがゆえにできないことは、この作品でほとんど描かれていません。
津田も(作品序盤の)沙織も、単純にお客さんとしてしか捉えていません。
津田は言いました。
「この社会は障がい者にとって、とても暮らしにくい」
沙織は吐き捨てました。
「普通ってなんだよ!何が違うんだよ」
この映画は障がい者に対して優しい社会でありましょうとか、立場を思いやりましょうとか、そういうスタンスで取られたものではないと思います。
そもそも区別する必要って本当にあるんだっけ?と僕たちに自問の機会を与えてくれる映画です。
固有名詞を出して申し訳ありませんが、チャリティーとか感動を謳いながら障がい者を「区別」している24時間テレビのような切り取り方に嫌気がさしている方にはハマる作品かもしれません。
健司との逃避行で急に映画っぽさが出てしまったのが(作品として動きをつけないといけないのはわかります)ちょっと残念でした。