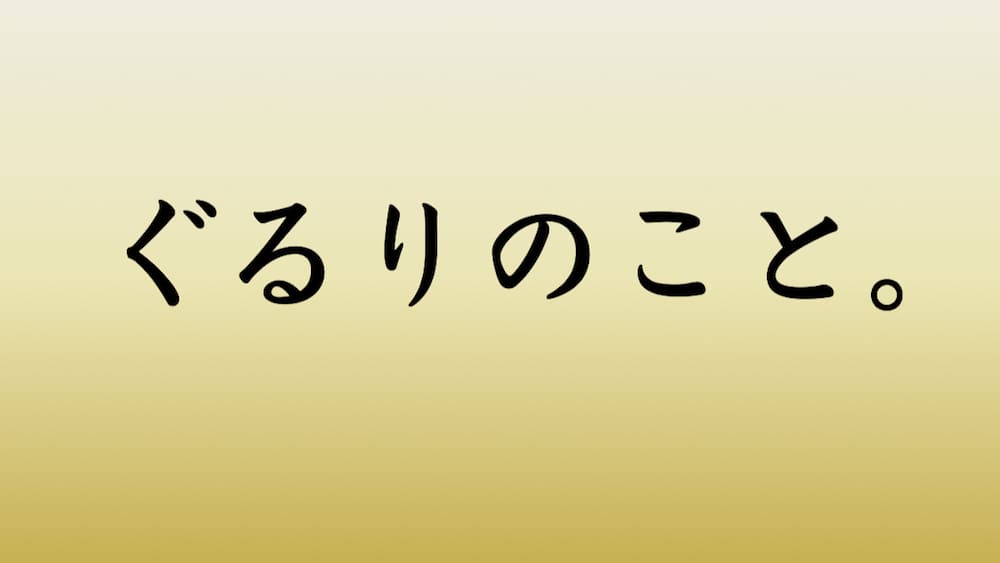こんにちは。織田です。
2008年の映画『ぐるりのこと。』を鑑賞しました。木村多江、リリー・フランキーがともに初主演となった作品です。
原作、脚本、編集、監督は橋口亮輔。
第一子が生後間もなく死んでしまった両親の苦悩と闇、また生きていくことの難しさを描いています。
『ぐるりのこと』のスタッフ、キャスト
監督・原作・脚本:橋口亮輔
佐藤翔子:木村多江
佐藤カナオ:リリー・フランキー
吉田波子:倍賞美津子
安田邦正:柄本明
吉田勝利:寺島進
吉田雅子:安藤玉恵
諸井康文:八嶋智人
吉住栄一:寺田農
夏目先輩:木村祐一
橋本浩二:斎藤洋介
和久井寛人:温水洋一
田中ツヨシ:加瀬亮
弁護士:光石研
裁判長:田辺誠一
あらすじ紹介
1993年、何事にもきちょうめんな妻の翔子(木村多江)と法廷画家の夫カナオ(リリー・フランキー)は、子どもを授かった幸せをかみしめていた。どこにでもいるような幸せな夫婦だったが、あるとき子どもを亡くしてしまい、その悲しみから翔子は心を病んでしまう。そんな翔子をカナオは温かく支え続け、2人の生活は少しずつ平穏を取り戻してゆく。
できることは信じることのみ
小さな出版社に勤める翔子(木村多江)と、靴屋をたたみ法廷画家として生きるカナオ(リリー・フランキー)の夫婦を中心に描かれたヒューマンドラマ。舞台は1993年からの10年間のようです。
上述したように第一子が出産直後に亡くなり、翔子は心を病んでしまいます。仕事を辞め、引っ越し、一人の時間を増やしてはみたものの自分の感情をコントロールできなくなってしまいました。
出産前は何事も決めないでフラフラと生きるカナオを翔子が管理して形式的には夫婦の体裁をとっていました。しかし、翔子がうつ病になってからはカナオはただ翔子の癇癪や衝動を抑え、信じることしかできませんでした。
むしろその唯一のできることである、「信じる」を貫いたカナオの懐の深さをこの映画では見せたかったのかもしれません。
以下、ネタバレが含まれていますのでご注意ください
映画のネタバレ感想
以下、作品のネタバレや展開に触れていきます。未見の方はご注意ください。
旦那は天性の女たらし
まず、カナオについて。
作中でしばしば描かれますが、彼は天然の女たらしです。本人が意図しているのかはわかりませんが、絵画教室で女性の生徒と目を合わせて接近したり、靴屋で若い女の人に「飯行くか」と声をかけたりと、翔子が管理したくもなるような、ふらつきぶりでした。関西弁と九州弁が混ざったような口調も特徴出来でしたね。
『夢売るふたり』の貫也(阿部サダヲ)にも少し似ているように感じます。
カナオと翔子の結婚前の描写は、翔子が夜の営みの頻度や帰宅時間をきっちり管理する形でした。機械的に決められたセックスに対してカナオはそれがルール化、マスト化しないように案を出します。たまには口紅をつけてよ、とか。
何事も決めたがる翔子と、動きたがるカナオ。このどちらに移入できるかで作品の見方は変わってきそうな気もします。個人的にはどちらの言い分もわかりますが。
翔子がふさぎ込んでしまってからのカナオは、自らのエゴを消して彼女の支えだったり癇癪のはけ口だったりになろうと努力していました。
彼も彼なりに、だらしがないとか、頼りないとか翔子の肉親に言われていたことも認識していたはずです。
翔子が切れてしまった一方で、カナオが切れずに生活を続けられたことが、佐藤家がなんとか持ちこたえた理由かなと思います。
切れてしまった妻
一方で翔子にとっては辛い描写が続きました。
生まれてきた子どもとの死別により、彼女には小さな生命への畏怖が刷り込まれ、自分がどうやって人生を過ごしていけばいいかわからなくなってしまいました。
他人の結婚生活や家族生活に対して、とげとげしさと乾いた笑いと引きつった表情でしか感情を表現できなくなった翔子。メンヘラ扱いするのは簡単ですが、母親が生命を失うことの重さを描いています。
先述の通り、夜の営みにも規則性や計画性を求めて翔子は過ごしてきました。線路を敷き、暗い夜も前方を照らしながら彼女は進んできました。
突如脱線して訪れた闇の中で、彼女は光を照らすすべを見失い、また闇に潜むものすべてを敵のように感じたのではないでしょうか。手を差し伸べ続けたカナオに寄りかかることができるようになったのは作品の最終盤でした。
スポンサーリンク
社会派作品の代償
法廷画家(カナオ)の部分にもかなり比重が置かれている本作。
猟奇的な殺人や猛毒テロなど実際にあった事件をオマージュした裁判が繰り返されます。
『ぐるりのこと。』は佐藤夫婦を中心とした周囲を描いた作品ですが、裁判シーンはあくまでカナオの仕事先の日常です。
カナオが何かを感じ取ることもなければ翔子にフィードバックすることもありません。それでも橋口監督は毎日起きている社会的な一コマとして描きたかったのでしょう。加瀬亮や新井浩文など実力派の役者を使っているところも注目です。
記者はなぜ我先にと急いで退廷するのか。
傍聴席から証人尋問はどう見えるのか。
サイコパスの犯罪者はどんなことを口走るのか。
色々な場面があるなかで、あなたはどう思うか?と橋口監督に問いかけられている気がしました。
法廷画家については榎本よしたかさんのQ&Aが面白かったので興味がある方はどうぞ。
寺島進と安藤玉恵が演じた(翔子の)兄夫婦に不器用な人間臭さが見えた一方で、周囲を見下したような母(倍賞美津子)の人間臭さは最後まで好きになれませんでした。
でも、この母親を切り捨てずに残したところが本作の希望であり、また家族というものの絆と面倒さの証明なのかもしれません。
橋口監督の、市井をこちらに余すことなく伝えよう、という意志は強く感じられました。
ただし映画なのでどうしてもドキュメンタリーとはならず、象徴的なシーンの数々が一人歩きしたかなという印象は受けました。